1日何杯まで?コーヒーの飲み過ぎによるリスクと今日からできる対策
- 仕事や家事の合間についコーヒーを飲み過ぎてしまう
- コーヒーを飲んだ後はなぜか眠れない
- 結局1日に何杯まで飲んでいいのかはっきり知りたい
コーヒーを飲み過ぎて体調を崩したことはありませんか?この記事では、コーヒーの飲み過ぎによる症状や飲み過ぎを防ぐためのポイント、コーヒーの健康効果などを解説します。記事を読めば、コーヒーのメリットを最大限に活かし、健康的な毎日が送れるようになります。
飲んでも良いとされているコーヒーの量は、健康な成人で1日当たりマグカップ3〜4杯程度です。カフェインの量を意識し、飲み方を工夫することでコーヒーを健康的に楽しめます。
もくじ
コーヒーの飲み過ぎで現れる症状

コーヒーの飲み過ぎが原因で現れる症状は、以下のとおりです。
- 不眠
- 下痢・腹痛
- 頭痛・めまい
- 貧血
- 自律神経の乱れ
- 骨粗鬆症などの病気
いずれの症状も、コーヒーに含まれるカフェインが主な原因です。
» コーヒーは体に悪いと言われる4つの理由!健康的な飲み方も紹介
不眠
コーヒーを飲み過ぎると、カフェインの影響で眠れなくなることがあります。不眠の具体的な症状は、以下のとおりです。
- 布団に入ってもなかなか寝つけない
- 夜中に何度も目が覚めてしまう
- ぐっすり眠った気がしない
カフェインの作用は数時間続くので、夕方以降にコーヒーを飲むと、睡眠に影響が出やすくなります。質の高い睡眠をとるためには、寝る前のカフェイン摂取を控えましょう。
下痢・腹痛

コーヒーの飲み過ぎは、下痢や腹痛を引き起こすことがあります。コーヒーに含まれるカフェインが胃酸の分泌を促し、胃の粘膜を刺激するためです。コーヒーにより腸の動きも活発になるため、下痢になることもあります。
空腹時にコーヒーを飲んだり、大量の冷たいコーヒーを一度に摂取したりすると、下痢や腹痛の症状が出やすくなります。ストレスや疲労も、カフェインの影響を受けやすくなる要因です。コーヒーの摂取量には注意しましょう。
頭痛・めまい
コーヒーの飲み過ぎは、頭痛やめまいを引き起こすことがあります。カフェインの血管収縮作用や、カフェインが切れたときの血管拡張が、頭痛やめまいの原因です。日常的にカフェインを摂っている人が、カフェインの摂取量を減らしたり摂取をやめたりすることで、頭痛が出ることもあります。
カフェインの過剰な摂取は自律神経のバランスを崩し、めまいやふらつきの原因にもなります。カフェインの利尿作用による脱水症状から、立ちくらみのようなめまいが引き起こされることもあるので、注意しましょう。
頭痛やめまいは、集中力の低下や体のだるさにつながり、日常生活のパフォーマンスを低下させます。
貧血

コーヒーにはタンニンという成分が含まれており、大量に摂取すると貧血を引き起こす恐れがあります。野菜や豆類などに含まれる鉄分は、タンニンの影響を受け、体内に吸収されにくくなるためです。食事中や食後すぐにコーヒーを飲むことは避けましょう。
鉄分不足によって現れる症状は、以下のとおりです。
- めまい・立ちくらみ
- 倦怠感・疲労感
- 顔色不良
- 動悸・息切れ
月経のある女性や妊娠中、授乳中の女性は貧血リスクが高まるので、コーヒーの摂取量に注意してください。
自律神経の乱れ
カフェインを過剰に摂取すると自律神経(※1)の乱れにつながるので注意が必要です。カフェインは交感神経(※2)を刺激し、集中力を高めたり眠気を覚ましたりする効果があります。自律神経の乱れは、不安感やイライラ、焦燥感などを感じさせ、動悸や息切れ、手の震えなど生活に悪影響を及ぼします。
自律神経の乱れを防止するために、コーヒーを飲む量やタイミングを見直しましょう。
※1 自律神経とは、身体の活動を自動的に調整している神経系のことで、交感神経と副交感神経の2種類があります。
※2 交感神経とは、自律神経系の一種で、活動的な状態や緊張状態、ストレス時などに働く神経です。心拍数や血圧を上げたり、筋肉を緊張させたり、汗を分泌させたりすることで、身体の機能を活発化させます。
骨粗鬆症などの病気
コーヒーの飲み過ぎは、骨粗鬆症(※3)などの病気につながる可能性があります。カフェインには、カルシウムを、尿と一緒に体の外へ排出しやすくする働きがあります。体内のカルシウムが不足すると、骨の密度が低下し骨が弱くなることが原因です。
高齢の方や閉経後の女性は、もともと骨粗鬆症のリスクが高いため、コーヒーの飲み過ぎには注意しましょう。
※3 骨粗鬆症とは、骨の量が減少し骨がもろくなって骨折しやすくなる病気です。一般的に高齢の女性に多く、若年層でも生活習慣によって発症することがあります。
コーヒーの飲み過ぎを防ぐためのポイント

コーヒーの飲み過ぎを防ぐためのポイントは、以下のとおりです。
- カフェインの含有量を意識する
- カフェインレスコーヒーを活用する
- 他のカフェイン入り飲料にも注意する
- コーヒーの代替飲料を見つける
各ポイントを意識することで、体に負担をかけずにコーヒーと上手に付き合えます。
カフェインの含有量を意識する
コーヒーの飲み過ぎを防ぐには、自分がどれくらいのカフェインを摂っているか意識する必要があります。自分が飲んでいるコーヒーにどれくらいカフェインが含まれているかを把握すれば、カフェインの摂り過ぎを防げます。
1日当たりに摂取していいカフェインの適量は一般的に400mg未満です。カフェインの作用は個人差があるので、少しずつ飲んで体調を確認するようにしてください。
» 缶コーヒーに含まれるカフェイン量や適切な摂取量を解説
カフェインレスコーヒーを活用する
コーヒーの飲み過ぎを防ぐために、カフェインレスコーヒーの活用も検討してみてください。カフェインレスコーヒーなら、カフェインの摂取量を気にすることなくコーヒーの香りや味わいを楽しめます。コーヒーは好きだけどカフェインの摂りすぎを避けたい人は、カフェインレスコーヒーを選びましょう。
妊娠中や授乳中のお母さんや、カフェインで胃が荒れやすいと感じる人にもカフェインレスコーヒーはおすすめです。カフェインレスコーヒーを取り入れることで、コーヒーを健康的に楽しめます。
他のカフェイン入り飲料にも注意する

健康的な生活を送るためには、コーヒー以外の飲み物にも注意が必要です。普段何気なく飲んでいるものにも、カフェインや糖分が含まれていることがあります。カフェインや糖分に注意したい飲み物は、以下のとおりです。
- 紅茶・緑茶・烏龍茶
- エナジードリンク・栄養ドリンク
- 清涼飲料水・ジュース
- ココア
紅茶や緑茶、ウーロン茶といったお茶にもカフェインは含まれています。エナジードリンクや栄養ドリンクは、製品によって多くのカフェインや糖分を含んでいるので、飲む前に成分表示を確認しましょう。ドリンクによっては、知らないうちにカフェインを摂り過ぎてしまうこともあるため注意が必要です。
糖分の多い清涼飲料水やジュースは、血糖値の急な変動や体重増加につながります。ココアにはカフェインに似た働きをするテオブロミンという成分が含まれています。ココアを就寝前にたくさん飲むのは控えましょう。
コーヒーの代替飲料を見つける
コーヒーの飲み過ぎを防ぐためには、コーヒーの代わりになる飲み物を見つけましょう。気分や体調に合わせて飲み物を選べると、カフェインの摂取量を自然と調整しやすくなります。コーヒーの代わりになる飲み物は、以下のとおりです。
- カフェインレスコーヒー
- ルイボスティー
- 麦茶
- たんぽぽコーヒー
- ココア
ハーブティーや白湯なども、コーヒーの代替飲料に向いています。無理なくコーヒーの量を減らすために、自分のお気に入りの飲料を見つけましょう。
1日当たりの適切なコーヒー摂取量

カフェインの影響は体質により異なり、コーヒーを毎日楽しむには適切な量を知る必要があります。1日当たりの適切なコーヒー摂取量は、健康な大人で1日にマグカップ3〜4杯、妊娠中・授乳中は1〜2杯が目安です。
コーヒーの種類や淹れ方、他のカフェイン飲料の摂取量も考慮する必要があります。体調を観察しながら、自分に合った量でコーヒーを楽しみましょう。
» コーヒーは1日何杯まで?飲み過ぎのリスクや注意点を解説
コーヒーの健康効果

コーヒーの健康効果は、以下のとおりです。
- リラックス効果
- 疾病予防効果
- 覚醒効果
- ダイエット効果
- 肝機能障害の抑制
- 生活習慣病の予防
- むくみ予防
- 消化機能の促進
コーヒーと上手に付き合うことで、健康的な生活を送れるようになります。
リラックス効果
心を落ち着かせ、リラックスさせる効果がコーヒーにはあります。コーヒーの香ばしい香りや温もりに包まれることで、自然と緊張がほぐれ気分転換にもなります。コーヒーを淹れたり飲んだりするひとときは、忙しい毎日の中でほっと一息つける大切な時間です。
適度な量のカフェイン摂取は疲労感を和らげ、気分を穏やかにする効果もあります。コーヒーは手軽に心身をリセットする習慣としておすすめです。
疾病予防効果
コーヒーの健康効果として、疾病予防があります。コーヒーによって予防が期待できる疾病は、以下のとおりです。
- 2型糖尿病
- 特定のがん(肝臓がんや大腸がん、子宮体がんなど)
- パーキンソン病
- アルツハイマー型認知症
- 脳卒中
- 心臓の病気
- 痛風
コーヒーには疾病予防効果が期待できますが、過剰摂取は健康を害する恐れがあります。コーヒーの過度な摂取には気をつけましょう。
覚醒効果
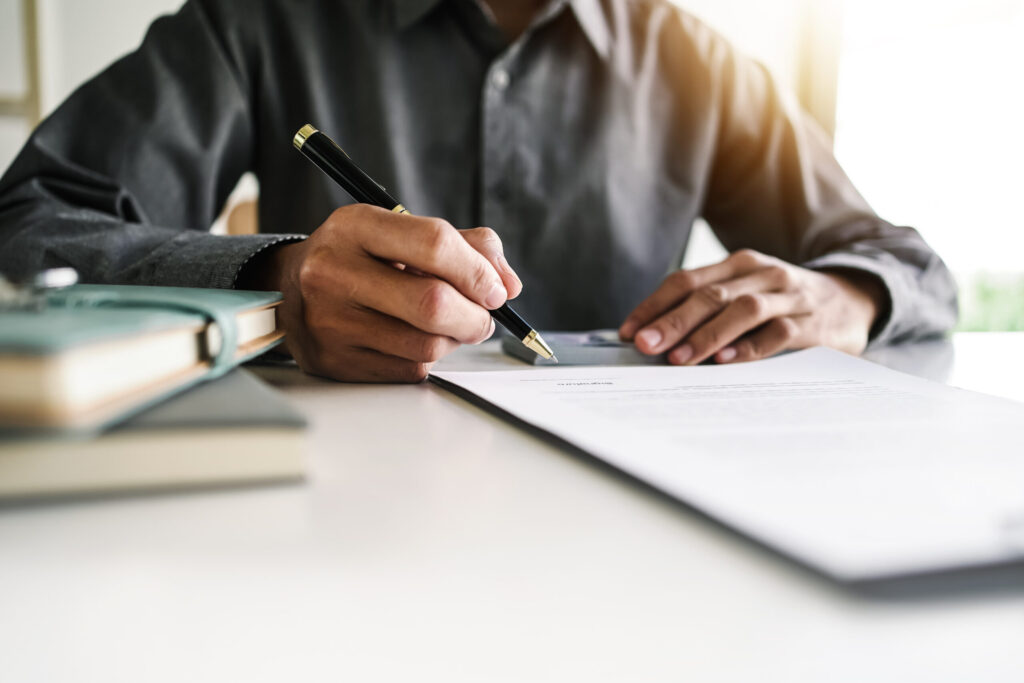
コーヒーを飲むと、頭がシャキッとして集中しやすくなる効果が期待できます。コーヒーに含まれるカフェインには、覚醒効果があります。コーヒーの覚醒効果によるメリットは、以下のとおりです。
- 眠気覚醒
- 集中力向上
- 記憶力向上
- 注意力向上
- 疲労感軽減
- 作業効率化
- 運動能力向上
コーヒーの覚醒効果を活用することで、日常生活のさまざまな場面でパフォーマンスの向上が期待できます。
ダイエット効果
コーヒーに含まれるカフェインやクロロゲン酸には、ダイエットをサポートする働きがあります。カフェインは脂肪の燃焼を促し、クロロゲン酸は脂肪の吸収を抑え、体内の脂肪分解を助ける効果が期待されています。
コーヒーは基礎代謝の向上や運動パフォーマンスの改善が期待でき、ダイエットに効果的です。人によっては、コーヒーにより食欲が一時的に抑えられることもあります。ダイエットを考えている人は、上手にコーヒーを取り入れましょう。
肝機能障害の抑制
コーヒーに含まれる成分には、肝臓を保護し働きを助ける効果が期待されています。コーヒーを飲むことによって期待できる肝臓へのメリットは、以下のとおりです。
- 特定肝臓病リスクを軽減する
- 肝細胞を保護する・炎症を抑制する
- 脂肪肝・線維化を抑制する
- ウイルス性肝炎の進行を抑制する
- 肝機能検査値を改善する
生活習慣病の予防

コーヒーは、生活習慣病の予防も期待できます。コーヒーに含まれるポリフェノールなどの成分が、体を病気から守る働きをしてくれるためです。
ポリフェノールが動脈硬化のリスクを軽減させたり、2型糖尿病や肝硬変などのリスクを下げたりすると研究で示されています。定期的にコーヒーを飲むことで、脳卒中など、一部の心血管系疾患のリスクを下げる可能性があります。
むくみ予防
コーヒーは、むくみ予防にも効果的です。カフェインやカリウムが、体内の水分バランスを整える働きをしてくれるためです。
カフェインには利尿作用があり、体の余分な水分や老廃物の排出を促します。血行を良くする効果も期待できるため、水分の巡りがスムーズになり、むくみの軽減につながります。カリウムは、体内の塩分と水分のバランスを調整してくれるため、コーヒーはむくみ対策におすすめです。
消化機能の促進
コーヒーは、食後の消化をスムーズにする働きが期待できます。カフェインが胃の消化液の分泌を促し、胃や腸の活動を助けるからです。胃腸の動きが活発になることで栄養の吸収効率が上がり、食後の胃もたれを和らげる効果も期待できます。
腸の蠕動運動も促されるため、便通が良くなることもあります。消化機能を整えるには、食後のコーヒーがおすすめです。
まとめ

コーヒーはリラックス効果や病気予防などのメリットがある一方、飲みすぎると不眠や腹痛、貧血などの不調を招く恐れがあります。コーヒーの摂取量の目安は1日当たりマグカップ3〜4杯、妊娠中・授乳中は1〜2杯です。
適切な摂取量を守ることやカフェインの量を意識すること、代替飲料を活用することで、コーヒーの飲み過ぎを防げます。コーヒーのメリットとデメリットを理解し、自分の体調と相談しながら健康的にコーヒーを楽しみましょう。

